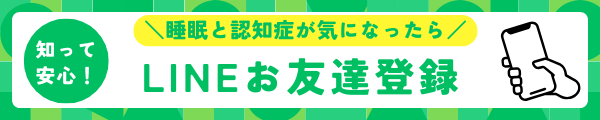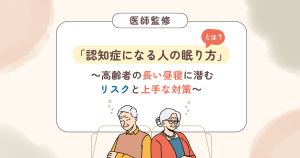【医師監修】高齢者の不眠はメラトニンが原因? 認知症症状を見逃さないために
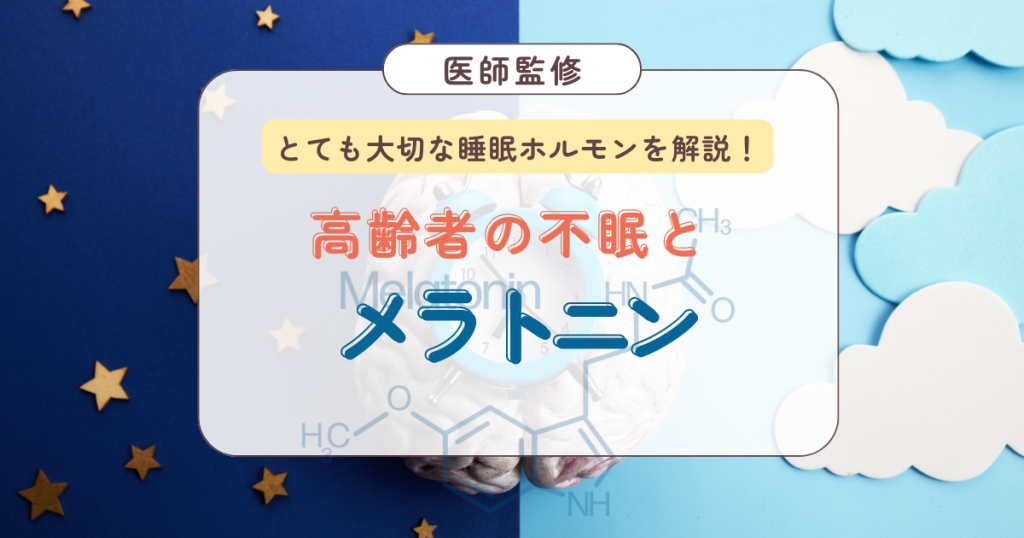
当記事は、東京センタークリニック 院長 長嶋 浩貴 先生にご監修いただきました。
【医師監修】「最近、夜なかなか眠れない」「早朝に目が覚めてしまう」――
そんな“眠りの変化”を感じていませんか?加齢によるメラトニンの分泌低下が原因のひとつといわれています。
不眠が続くときは、認知症の初期変化(MCI)が関係している場合もあります。
本記事では、高齢者の不眠とメラトニンの関係、そして早期に気づくためのポイントを解説します。
目次
はじめに
「高齢になると眠りが浅くなりやすい」とよく聞きますが、その原因のひとつに“メラトニン”というホルモンの分泌低下があると示唆されています。実際に、
- 夜になかなか眠れない
- 夜中に何度も目が覚める
などの不眠に悩む高齢者は少なくありません。さらに、不眠が続く背景には、認知症初期(軽度認知障害:MCIを含む)の変化が影響している可能性も指摘されています。
自分自身が認知症初期にあると気づかないまま、不眠症状だけが先に表れるケースもあるといわれています。
本記事では、高齢者の睡眠が乱れやすい理由と認知症初期とのつながり、そして日常生活でできる対策や専門医の受診タイミングについてご紹介します。
なぜ高齢者は不眠になりやすい? メラトニンと加齢の関係
メラトニンとは
メラトニンは、脳内の松果体という部位で作られるホルモンで、夜になると分泌量が増加し、自然な眠気を誘発する役割があります。

加齢によるメラトニン分泌低下
若い頃に比べ、高齢者は夜間のメラトニン分泌が低下しやすいと報告されています。その結果、
- 寝付きが悪い
- 夜中に目が覚めやすい
- 早朝に目が覚めてしまう
など、睡眠が十分取れない状態に陥りやすいと考えられます。
さらに、メラトニンの分泌リズム自体が乱れると、昼夜の区別がつきにくくなり、「昼夜逆転」のような睡眠パターンにつながる可能性があります。
不眠が認知症初期と重なると起こりうること
軽度認知障害(MCI)と睡眠の関係
「軽度認知障害(MCI)」とは、日常生活に大きな支障を来さないものの、認知症へ進行するリスクが通常より高い状態を指します。
MCIを含め認知症の初期段階では、脳の一部で微妙な機能低下が始まっており、これが睡眠覚醒リズムを司る領域にも影響すると考えられています。
不眠が脳へ及ぼす影響
深い眠り(ノンレム睡眠)が不足すると、
- 日中にぼんやりする
- 物忘れが増える
- 集中力が落ちる
などの症状が続き、認知機能の低下にさらに拍車をかけてしまうかもしれません。
関連記事
【医師監修】認知症初期の方が良質な睡眠をとるコツ5選〜昼間の行動と隠れた原因対策で、夜ぐっすり眠るために〜
メラトニンを整える生活習慣:具体的なアプローチ
朝の光を浴びて体内時計をリセット
- 朝起きたらカーテンを開け、自然光をしっかり浴びる
- 規則正しい睡眠リズムを作る
昼間に適度な運動を取り入れる
- ウォーキングや軽いストレッチを行う
- 太陽の光を浴びながら運動する
昼寝は短時間にとどめる
- 昼寝は30分以内に抑える
- 午後3時以降は避ける
夜間のブルーライトをできるだけカット
- 就寝の1〜2時間前から電子機器の使用を控える
- ブルーライトカットの設定を活用する
規則的な生活リズムを意識
- 食事や就寝・起床の時間を一定に保つ
- 生活リズムを乱さない工夫をする
メラトニンはサプリや薬で補えるのか? 日本での現状
日本では適応がまだ限定的
海外ではメラトニン配合のサプリが市販されていますが、日本では医薬品として扱われ、サプリとして自由に購入できません。
有効性・安全性は研究段階
メラトニン補充の有用性については研究途上であり、慎重な判断が必要です。
医療機関や治験での情報収集が大切
認知症初期を疑ったら:受診のタイミングと治験の選択肢
不眠が続く場合は専門医に相談を
長期間の不眠や物忘れ、集中力の低下が見られる場合は、専門医の受診を検討しましょう。
治験への参加という選択肢
○メリット
- 新しい治療法に早い段階でアクセスできる可能性
△ デメリット
- 効果や安全性が十分に確立されていない場合がある
参加を検討する際は、担当医や治験コーディネーターとよく話し合いましょう。
記事のまとめ
不眠が続く場合には専門医への相談や治験の相談も視野に入れる
- 高齢者の不眠はメラトニンの分泌低下による体内リズムの乱れが大きく関与
- 認知症初期の変化が加わると、さらに睡眠が浅くなりやすい
- 生活習慣の見直しが重要
- 不眠が続く場合は、専門医への相談や治験の活用も視野に入れる
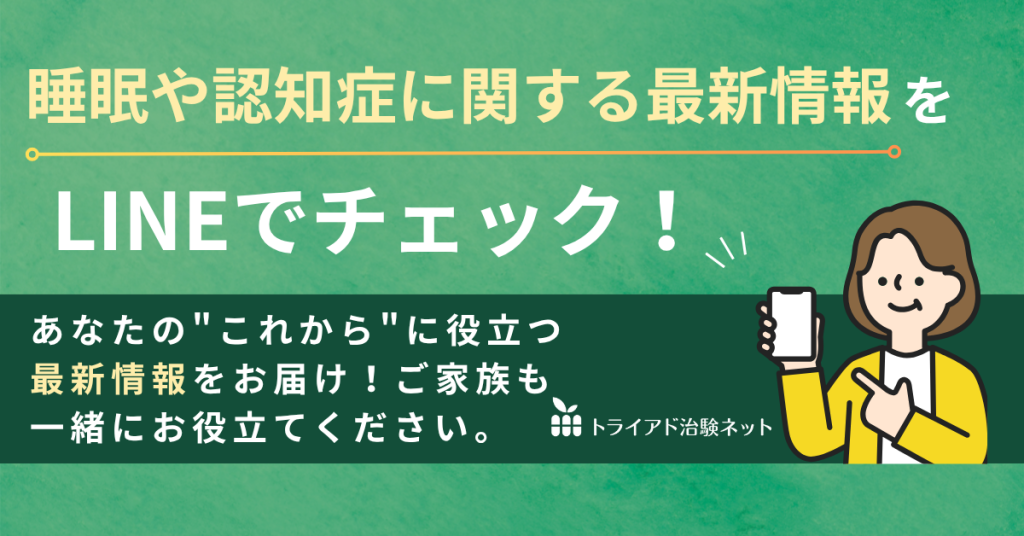
参考文献
- Melatonin: A potential nighttime guardian against Alzheimer’s. Molecular Psychiatry, 30, 237–250 (2025)

監修医師
東京センタークリニック 院長 長嶋 浩貴
Hirotaka Nagashima
千葉大学医学部卒業後、東京女子医科大学循環器内科に入局。ハーバード大学医学部での研究経験を経て、東京女子医科大学で血管研究室長を歴任。その後、350以上の治験に携わり、2017年には日本初の分散型治験を実施。現在は東京センタークリニック院長として、認知症を含む多くの臨床研究に取り組む。
東京センタークリニックHPはこちら