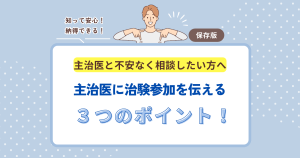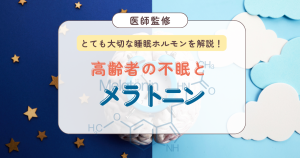夜中に何度も目が覚める… 見逃しがちな認知症初期のサインとは?【医師監修】

当記事は、東京センタークリニック 院長 長嶋 浩貴 先生にご監修いただきました。
夜中に何度も目が覚めるのは、加齢だけではないかもしれません。認知症初期(MCI)や概日リズムの乱れが関係している可能性も。朝や日中の眠気・イライラが続く方は、専門医に相談を。認知症+睡眠のお悩みに関する最新の情報と対策をご紹介します。
目次
夜中に目が覚める…「年のせい」だけではない?
「夜中に2回以上起きてしまう…年を取ると仕方ない」と思い込んでいませんか?
実際、高齢になると睡眠が浅くなる・早寝早起き傾向になるなど、加齢による変化は確かに存在します。しかし、夜間の覚醒や早朝覚醒が重なり、朝や日中に強い眠気や疲労感が続いている場合は、加齢だけが原因ではない可能性も十分に考えられます。厚生労働省の「健康づくりのための睡眠指針2023」でも、睡眠時間(量)と睡眠休養感(質)の両立が健康寿命を延ばすうえで重要だと示されており、特に高齢者の“昼夜のメリハリ”が大切であることが強調されています。もし朝~日中にも“気になる症状”があるなら、認知症初期(MCI含む)や体内リズムの乱れが関わっている可能性があります。
高齢者の睡眠変化と生活習慣のポイント
加齢に伴う睡眠の特徴
- 深い眠りが減って夜中に目覚めやすい
トイレに起きたり、ちょっとした物音でも目覚めてしまうことが増えがちです。 - 睡眠リズムが前倒しに
早寝早起き傾向になり、朝方4~5時など非常に早い時間帯に目が覚める「早朝覚醒」も多くなります。
日中のメリハリが鍵
「健康づくりのための睡眠指針2023」では、健康的な睡眠を得るための具体的な工夫として、以下のようなポイントが挙げられています。
- 8時間以上寝床で過ごさない
- 昼間は長時間の昼寝を避け、運動習慣を取り入れる
- 寝る前にスマホやTVを長時間見ない
- 寝室は暗くて静かな心地よい温度に
- カフェインやお酒、タバコは控えめに
特に高齢者は、夜中に長くベッドにいることで“浅い睡眠”の時間が増えてしまう傾向があります。日中の活動量を増やし、夜にしっかり眠るための環境作りを意識してみましょう。
朝~日中の症状がポイント—「強い眠気」は要注意
夜中に目が覚めるだけなら、年齢相応の睡眠変化かもしれません。しかし、朝や日中にも以下のような症状が重なっていませんか?
午前中の強い眠気・だるさ
- 起きても頭がぼーっとして活動意欲が出ない
- 家事や外出などの用事をこなす気力がない
- 十分寝たはずなのに休養感が得られない
「健康づくりのための睡眠指針2023」によれば、時間(量)だけでなく休養感(質)も重視すべきとされています。午前中から強い眠気が続くようであれば、夜間の睡眠が実質的に十分取れていない可能性が高いです。
30分以上の昼寝が習慣化
- 昼寝が長いと夜間の睡眠がさらに浅くなりやすい
- “寝不足だから昼寝してしまう”→“夜に眠れない”という悪循環が進む
睡眠指針では、日中の長い昼寝は避けることが推奨されています。短時間の昼寝は体に良い場合もありますが、30分を大幅に超えるような昼寝が毎日のように続くなら注意が必要です。
夕方~夜にイライラ・ソワソワ
- “サンセット症候群”と呼ばれるように、夕方以降落ち着かない状態が続く
- 家族に「夕方になると不機嫌で手がつけられない」と指摘される
日中のメリハリがついていないと、夕方~夜のコンディションが乱れてしまい、イライラ・不安感などが強まることがあります。
認知症初期・MCIで起こる睡眠リズムの乱れ
メラトニン分泌の低下
- 加齢でもメラトニン(睡眠ホルモン)は減少しますが、認知症やMCIの方は特に顕著に減りやすいといわれています。
- その結果、夜に眠れず昼間に眠くなるといった昼夜逆転が起こりがち。
「物忘れ」だけがサインではない
- 認知症というと、まず記憶障害(物忘れ)を想像しがちですが、睡眠リズムの乱れも初期段階でみられる重要な兆候のひとつ。
- 早めに対策すれば、生活の質(QOL)の維持や認知症の進行を遅らせる可能性が高まります。
チェックリスト—当てはまるなら早めの相談を
以下の項目に複数当てはまる方は、単なる“不眠”や“年のせい”だけでなく、認知症初期や体内リズムの乱れを疑ってみましょう。
夜間のチェック項目
- 寝付くのに30分以上かかる / 夜中に2回以上起きる
- 朝早く目が覚めるが、二度寝もできず疲れが取れない
朝~日中のチェック項目
- 午前中はずっと眠気・だるさが抜けない
- 30分以上の昼寝をほぼ毎日している
- 夕方や夜にイライラ・ソワソワして落ち着かない
もしいくつも当てはまるなら、生活習慣を見直すだけでなく、専門医への相談や認知症検査なども早めに検討しましょう。
既存の薬に対する注意点と、治験という選択肢
6従来の睡眠薬を使う際の課題
「健康づくりのための睡眠指針2023」では、睡眠環境や生活習慣の改善をまず推奨していますが、どうしても眠れない場合は薬を使うことも一つの方法です。ただし、認知症やMCIの方には以下のような懸念点があります
- 副作用(ふらつき・転倒リスクなど)のリスク
- 認知機能に影響を及ぼす可能性
- 服用をやめにくくなるケースも
新たな研究への期待—治験の活用
- 近年、体内時計を調整する薬の研究開発が進んでおり、夜間の中途覚醒や昼夜逆転を改善できる可能性が期待されています。
- こうした新薬を試すための治験が実施されることがあり、60~84歳で認知機能の低下を感じる方が対象となる例もあります。
- 必ずしも全員が参加できるわけではありませんが、専門医や治験情報サイトなどを活用することで、自分に合った選択肢を探ることができます。
-6-1024x536.png)
まとめ
- 夜中に何度も目が覚めるのは加齢だけが原因とは限りません。
- 「健康づくりのための睡眠指針2023」にあるように、睡眠時間と休養感の両立が大切ですが、朝や日中の強い眠気、長い昼寝、夕方のイライラなどが重なる場合は、認知症初期(MCI)や体内リズムの乱れを疑うべきです。
- 既存の薬を使う際は注意点も多いため、早めに専門医に相談し、生活リズムの見直しや治験などの新たな研究機会も含めて検討することが望ましいでしょう。
参考文献・出典
- 厚生労働省「健康づくりのための睡眠指針2023」
https://www.mhlw.go.jp/content/001288007.pdf

監修医師
東京センタークリニック 院長 長嶋 浩貴
Hirotaka Nagashima
千葉大学医学部卒業後、東京女子医科大学循環器内科に入局。ハーバード大学医学部での研究経験を経て、東京女子医科大学で血管研究室長を歴任。その後、350以上の治験に携わり、2017年には日本初の分散型治験を実施。現在は東京センタークリニック院長として、認知症を含む多くの臨床研究に取り組む。
東京センタークリニックHPはこちら