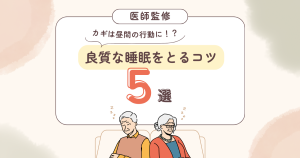【医師監修】高齢者の不眠を支える家族のために:認知症の可能性も視野に入れたサポート方法

当記事は、東京センタークリニック 院長 長嶋 浩貴 先生にご監修いただきました。
【医師監修】高齢者の不眠を支える家族のために:認知症の可能性も視野に入れたサポート方法
高齢の家族が夜更かしや寝付きの悪さに悩んでいるとき、当の本人には「不眠」という自覚がないことも珍しくありません。また、軽度な認知症の可能性が背景にある場合も考えられます。本記事では、不眠を自覚していない高齢者を家族がどのようにサポートし、どのように受診や治験の情報を探していくかについて解説します。
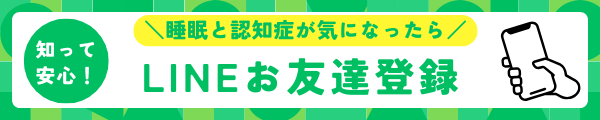
はじめに
高齢の家族が深夜に起きていたり、朝なかなか起きられず生活リズムが乱れていたりする場合、本人には「不眠」という自覚がないことも珍しくありません。単なる加齢による睡眠の変化なのか、それとも認知症の初期段階なのか――
早期に状況をつかむことで、家族が適切なサポートや受診につなげやすくなります。本記事では、高齢者の不眠に家族が気づいたとき、具体的にどのようなサポートができるのか、認知症の可能性を視野に入れる理由や治験情報の探し方などをまとめました。
本人が不眠を自覚していない場合の対応
夜間の様子や昼間の睡眠状況を客観的に記録する
- 夜中の状態を観察
本人に不眠の自覚がない場合、どのタイミングで起きているのか、どれくらいの時間目が覚めているのかを家族が把握することが大切です。
- 昼寝の長さや回数も確認
昼間に何度も長い昼寝をしていると、夜に眠れない原因になっている可能性があります。
- 記録のメリット
日々の眠りのパターンをメモやアプリなどで残すと、医師や看護師へ相談するときに具体的な状況を伝えやすくなります。
本人とのコミュニケーションを工夫する
- 自覚がないことを責めない
「眠れていないんじゃない?」と詰めるより、「最近夜中に目が覚めることが多いみたいだけど、体調はどう?」など、相手を尊重しながら話を切り出します。
- 家族自身もストレスをためない
不眠のサポートに集中するあまり、家族が疲弊すると共倒れになってしまうことも。周囲の協力を得ながら無理のない範囲で対応しましょう。
関連記事
「怒りっぽい」は認知症の初期症状かも? 不眠との関係と家族ができるサポート
認知症の可能性を視野に入れる理由
不眠と認知症の初期症状は見分けにくい
- 加齢による睡眠の変化との混同
高齢者はそもそも睡眠時間が短くなりがちですが、認知症の初期段階でも生活リズムが乱れ、夜に覚醒しやすくなることがあります。
- 物忘れや昼夜逆転といった兆候
早期受診のメリット
- 進行を遅らせる・症状を軽減できる可能性
認知症にはさまざまなタイプがありますが、早期に適切な診断・ケアを受けることで進行を遅らせたり、症状を緩和できたりする場合があります。家族の負担軽減にもつながる
不眠や認知症の疑いを早めに把握して対策をとると、介護負担や本人の不安感を軽減しやすくなります。
サポートの具体例
生活リズムの再構築
- 朝起きたら光を浴びる
カーテンを開けて日光を取り入れるだけでも体内時計を整えやすくなります。
- 日中の軽運動や趣味を取り入れる
散歩や体操、好きな趣味に取り組む時間を確保することで、夜にスムーズに眠りにつきやすくなる場合があります。
- 夕方以降の長い昼寝を避ける
夕方や夜に眠ってしまうと、夜間の睡眠に影響が出ることがあるため注意が必要です。
コミュニケーションの工夫
- 拒否感への対応
不眠を指摘されると本人が不快に感じる場合は、「こんな工夫をしてみたら、もっと寝やすくなるかもね」とポジティブに提案する姿勢が大切です。
もっと寝やすくなるかもね」とポジティブに提案する姿勢が大切です。
- 家族自身のケア
睡眠管理や認知症対応には家族の労力がかかります。自治体の相談窓口やケアマネージャー、訪問看護などを活用し、一人で抱え込まないようにしましょう。
受診や治験情報の探し方
不眠外来・認知症専門外来・かかりつけ医
- まずはかかりつけ医に相談
日々の体調や服薬状況を把握しているかかりつけ医は初期相談の窓口として有効です。必要に応じて専門外来に紹介してもらえます。
- 不眠外来や睡眠センター
症状が深刻な場合、睡眠の専門医や専用機器による検査を受けることで原因を特定しやすくなります。
- 認知症専門外来
物忘れや昼夜逆転など認知症が疑われる場合は、認知症専門外来や専門医への受診を検討しましょう。
治験情報を調べるコツ
公的機関や学会のサイトをチェック
治験募集情報は国の「臨床研究ポータルサイト」や各大学病院、学会のウェブサイトなどで公表されています。
- 現在薬を使っている場合でも相談可能
すでに睡眠薬を飲んでいる方でも、医師の判断で減薬や変更を検討できる場合があります。家族が「薬に頼らない方法も含めて考えてみよう」と声をかけることで、新たなアプローチを見つけられる可能性があります。
まとめ & 次のステップ
まとめ
高齢者の不眠は本人が気づかないまま進行し、認知症の初期症状と見分けにくいケースもあります。家族が日々の睡眠状況を観察・記録し、必要に応じて専門医や外来へ早めに相談することで、適切な診断・サポートにつなげやすくなります。
治験という選択肢も視野に入れておくと、より多角的なアプローチが可能です。
次のステップ
- まずはかかりつけ医や地域包括支援センターへ
手軽に相談しやすく、地域で受けられるサポートを教えてもらえます。
- 専門外来を活用する
不眠外来や認知症専門外来、医療機関の相談窓口で状況に合ったケアや検査を受けられます。
- 治験情報のリサーチ
公的サイトや大学病院のホームページをチェックし、気になる研究があれば主治医や窓口に問い合わせましょう。
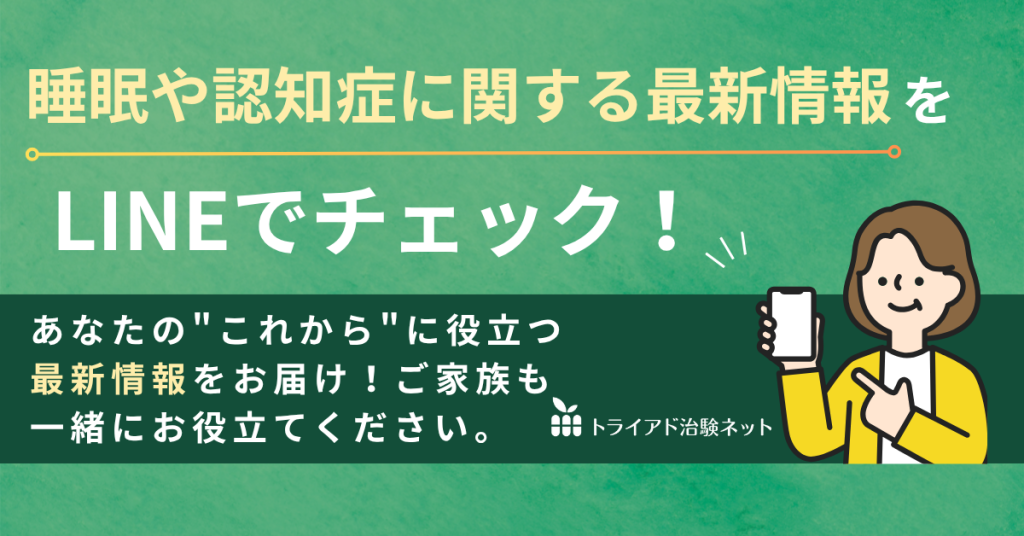

東京センタークリニック 院長 長嶋 浩貴
Hirotaka Nagashima
千葉大学医学部卒業後、東京女子医科大学循環器内科に入局。ハーバード大学医学部での研究経験を経て、東京女子医科大学で血管研究室長を歴任。その後、350以上の治験に携わり、2017年には日本初の分散型治験を実施。現在は東京センタークリニック院長として、認知症を含む多くの臨床研究に取り組む。
東京センタークリニックHPはこちら