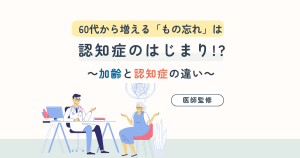【医師監修】「怒りっぽい」は認知症の初期症状かも? 不眠との関係と家族ができるサポート
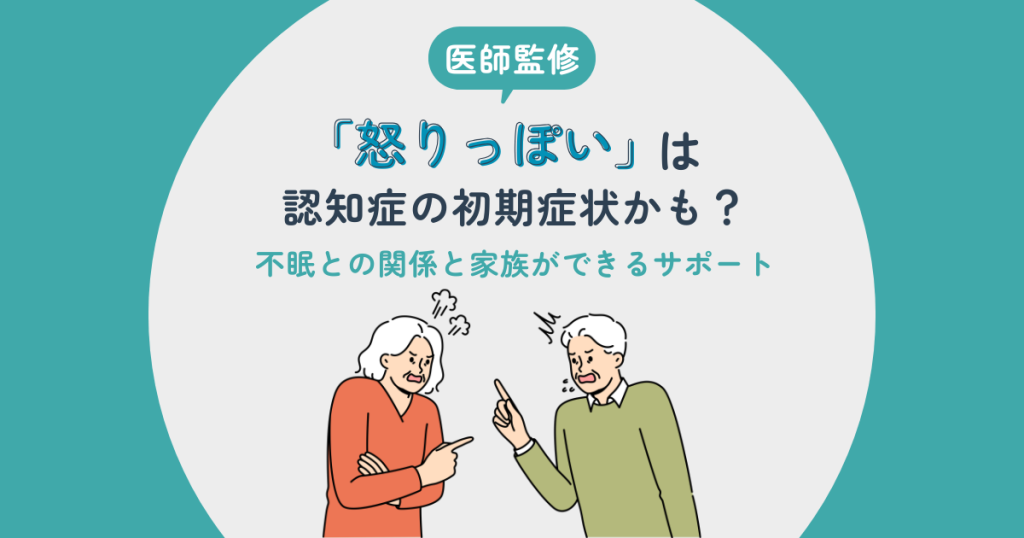
当記事は、東京センタークリニック 院長 長嶋 浩貴 先生にご監修いただきました。
【医師監修】「怒りっぽい」は認知症の初期症状かも? 不眠との関係と家族ができるサポート
高齢の家族が最近「怒りっぽい」「すぐに怒る」ようになった…それは認知症の初期症状かもしれません。不眠などの生活リズムの乱れが関係するケースも。本記事では、怒りっぽさと認知症の初期段階との関連、家族ができる具体的なサポート方法や治験情報の探し方を解説します。
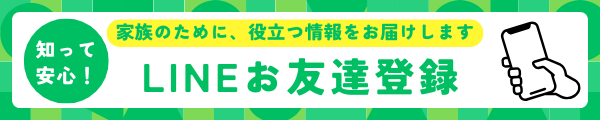
はじめに
最近、高齢の親がちょっとしたことで怒りっぽくなったり、同じ話を繰り返すようになったりしていませんか? こうした変化は、認知症の初期段階でよく見られる「行動・心理症状(BPSD)」のひとつである可能性があります。
特に軽度認知症~軽症の段階では、怒りっぽさやイライラ、不安感、口癖などが見られやすいため、家族としてはどう接したらよいか悩むことも多いでしょう。
本記事では、軽度認知症に多い“怒りっぽい”症状の背景や、家族が取り組める対策、さらには不眠や昼夜逆転との関連性、受診の目安などを幅広く解説します。早めに専門医へ相談することで症状が落ち着く例もありますので、ぜひ参考にしてください。
認知症初期における“怒りっぽい”症状の背景
なぜ怒りっぽくなるのか? 脳の変化と心理
認知症の初期段階では、記憶をつかさどる部分や判断能力を担う脳の領域に微細な変化が起こり始めます。これにより、物忘れや混乱が生じやすくなり、自分が置かれた状況を正確に理解するのが難しくなることがあります。
「聞いていない」「理解してもらえない」という思い込みから、不安や苛立ちが強まる。
周囲とのコミュニケーションがかみ合わず、本人もストレスを抱える。
こうした状態が続くと、些細な言葉や行動にも過敏に反応しやすくなり、結果として怒りっぽさや攻撃的な言動を引き起こす要因になるのです。
不眠や昼夜逆転がイライラを加速させる可能性
不眠や昼夜逆転があると、身体的にも精神的にも疲れがたまりやすくなります。
昼間にあまり活動しない → 夜の眠りが浅い → 日中も脳や身体が十分休まりきらない → さらにイライラが増す
このように生活リズムの乱れが、認知症初期のイライラを増幅させてしまうことも少なくありません。
家族ができる対処・対応のコツ
日常生活の見直しでイライラ予防
昼夜のメリハリをつける
- 昼間はできる範囲で散歩や体操など体を動かす時間を取り、太陽光を浴びることで体内リズムを整えます。
- 夜は照明を落とし、リラックスできる音楽やアロマなどを取り入れるなど、寝つきを良くする工夫をする。
室内環境を整える
- 室温や湿度、騒音、照明をチェックし、本人がリラックスできる空間を心がける。
- テレビやスマホの光刺激は、寝る1~2時間前には減らすのがおすすめ。
軽度な運動・レクリエーション
- 椅子に座ったままできるストレッチや音楽体操など、本人の体力に合わせて選ぶ。
- 適度に体を動かすと夜の寝つきが良くなりやすく、不安感やイライラの軽減にもつながります。
コミュニケーションのポイント
本人の気持ちを否定しない
- 「何度も同じこと言わないで」「そんなこと思い違いよ」と否定から入ると、ますますイライラが増す可能性があります。
- まずは「そうなんだね」「分かったよ」と一度受け止め、落ち着いて話を聞く姿勢を示しましょう。
会話のきっかけを上手に切り替える
- 怒りの矛先が自分や周囲に向かいそうなときは、軽い世間話や趣味の話題にシフトさせるのも手です。
- 大きな声で対応せず、ゆっくり低めのトーンで話すと落ち着きを取り戻しやすくなると言われています。
受診時のためにメモを取る
- イライラが起こったタイミングやきっかけ、1日の睡眠状況などを簡単にメモしておくと、医師に相談するときに役立ちます。
- 家族同士で情報を共有しておき、受診時にスムーズに伝えられるようにしておくとよいでしょう。
関連記事
【医師監修】なぜ認知症の初期に不眠を放置してはいけない?同時ケアの重要性と改善法
専門医への相談・受診の目安
性格変化と認知症初期の見極め
「年齢を重ねて性格が変わっただけ」と思いがちですが、明らかに以前より怒りっぽさが増したり、イライラの頻度や程度が生活に影響を及ぼすほどになってきた場合は、専門医への相談を検討しましょう。
軽度段階で受診することで、症状の進行を緩やかにできたり、不眠やストレスのケアを早期に始められる可能性があります。
どの科を受診すればいい? 受診前のチェックリスト
認知症の可能性が気になる場合の診療科:
- 物忘れ外来
- 神経内科
- 精神科
- 老年内科
受診時のチェックリスト例:
- イライラが起こりやすい時間帯やきっかけは?
- 不眠や昼夜逆転の有無(例:夜中に眠れず日中ウトウトしている)
- 物忘れや混乱、口癖が増えたなど、本人の変化をどの程度認識できているか
受診前にこうした情報をまとめておくと、医師とのやりとりがスムーズになります。
不眠とイライラを同時にケアする意義
良質な睡眠がもたらす心理面への好影響
良質な睡眠は脳の疲労回復や情動コントロールを助け、イライラや不安を和らげる方向に働くと考えられています。認知症初期には、特に睡眠障害が起き始める方が多く、不眠が続くと昼夜の感覚が混乱してしまいがちです。
睡眠リズムを整えることで、本人だけでなく家族の負担も軽減しやすくなる利点があります。
治験や最新の研究も視野に入れる
認知症に関する治験では、
行動・心理症状(BPSD)の変化や改善を含めたアプローチが試される場合もあります。軽度~軽症の段階なら、新しい治療法やサポートプログラムに参加しやすい可能性もあります。
- 公的機関や専門医から情報を得る
- 地域の医療機関や相談窓口、地域包括支援センターなどに問い合わせる
早めのアクションが、将来的な選択肢の幅を広げてくれるでしょう。
まとめ・呼びかけ
早めの対処で落ち着くこともある
軽度認知症の初期段階であっても、「怒りっぽさ」や「イライラ」が増えると家族は心配になるものです。しかし、専門医の診断と適切なケアを行えば、症状が落ち着くケースも珍しくありません。
- 日中の過ごし方や睡眠リズムを見直す
- 本人に寄り添った声かけ、コミュニケーションを心がける
- 必要に応じて早めに受診し、薬や生活面の助言を得る
こうした積み重ねによって、本人の状態が安定しやすくなる可能性があります。
家族だけで抱え込まない
認知症のケアは、家族だけで負担を抱えがちです。困ったときは、
- 主治医への相談
- 地域包括支援センターの活用
- 介護保険サービスを含む公的なサポート制度の利用
など、活用できる制度はたくさんあります。「こんなことで相談していいのかな?」と遠慮せず、早めに専門家や支援機関に声をかけることが大切です。
-6-1024x536.png)

東京センタークリニック 院長 長嶋 浩貴
Hirotaka Nagashima
千葉大学医学部卒業後、東京女子医科大学循環器内科に入局。ハーバード大学医学部での研究経験を経て、東京女子医科大学で血管研究室長を歴任。その後、350以上の治験に携わり、2017年には日本初の分散型治験を実施。現在は東京センタークリニック院長として、認知症を含む多くの臨床研究に取り組む。
東京センタークリニックHPはこちら