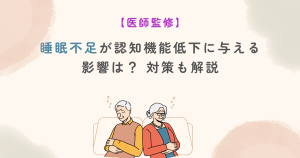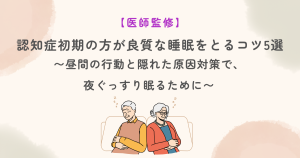【体験談】「母の物忘れが目立つ。でも“認知症”とは言いづらくて――」迷いを抱えた家族が“治験”という選択肢にたどり着くまで

「ここ1年ほど、母の物忘れが目立つようになった。でも、いきなり“認知症じゃない?”なんて切り出すのは、どうしてもためらってしまって」。そう語るのは、都内に暮らす会社員のAさん(仮名・40代)。
近所に住む義母(78歳)の認知機能の変化に気づきつつも、家族としてどのように向き合えばいいのか、答えが見つからないまま、時間だけが過ぎていったといいます。
そんな中、義母自身が口にした「夜中に目が覚めて、困っている」という一言が、ひとつの突破口になりました。
Aさんが、義母の発言をきっかけに「認知症と睡眠の関係」を調べていくと、高齢者の睡眠トラブルは、加齢による変化だけではなく、認知症の初期症状として現れることもあることがわかってきました。(▼こちらの記事に詳しい解説があります)
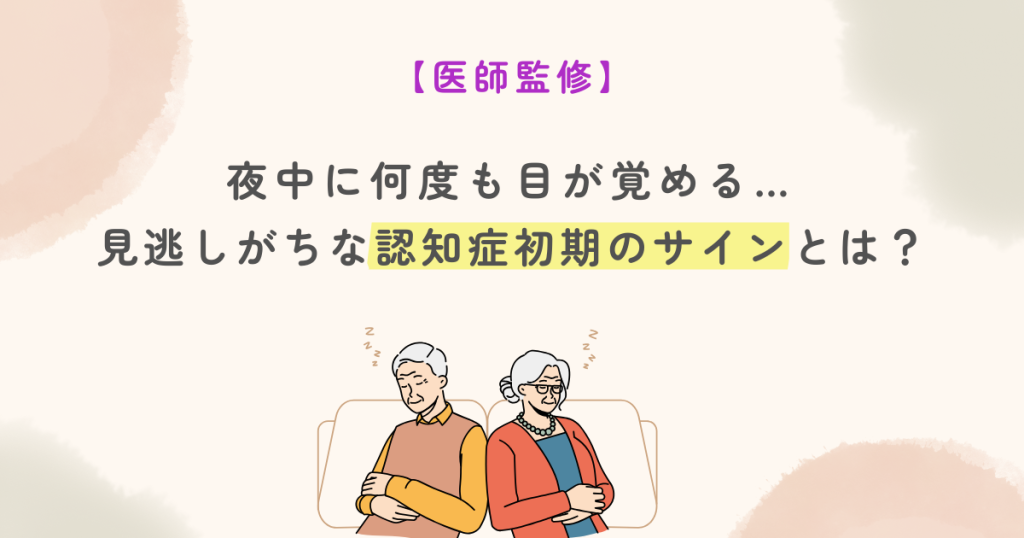
義母が繰り返す「眠れない」の背景にも「認知機能の低下があるのでは?」と感じたAさん。
さらに調べていくと、認知機能の低下がみられる高齢者でも安心して使える睡眠薬は、日本ではまだ治験段階でしか試せないことがわかりました。そこで、「睡眠の悩み」を入口に、治験という形で専門的なサポートを受ける道を家族で前向きに検討するようになったのです。
しかし、そこへ至るプロセスは簡単なものではありませんでした。
“治験”への戸惑いと抵抗感
「実験みたいで怖い」と不安を口にしたのは義父。見知らぬ場所での検査や、聞き慣れない“治験”という言葉に、戸惑いや警戒心を抱くのも無理はありません。
Aさん一家は、半年ほどの時間をかけて、少しずつ情報を集め、不安を共有しながら、ようやく「まずは一度、受診だけでもしてみようか」という気持ちにたどり着いたといいます。
実際の体験を通して見えてきたのは、受診のハードルを下げるためのヒントと、家族間で認知機能の変化について話すための、「きっかけ作り」の大切さです。
本記事では、Aさん家族のエピソードをもとに、治験の進め方やそのメリット、不安をどう乗り越えたのかを具体的に紹介していきます。

目次
きっかけは“夜中に目が覚める”―― 半年かけた家族の説得
Aさんの義母(78歳)は、1年ほど前から物忘れや金銭管理のミスが増え、家族の間では「そろそろ検査を…」という声が出始めていました。しかし義母は、「年齢のせい」と取り合わず、「認知症なんて絶対にならない」と強く拒否。
話題にするだけで怒ってしまうこともあり、Aさんは「家族みんなが心配しても、いざ本人に言うと“そんなわけない”と頑固に突っぱねられがちだった」と振り返ります。
そんな中、義母が訴えるようになったのが“夜中の覚醒”。
「毎晩3〜4時に目が覚めて眠れない。真っ暗で怖い」といった訴えが続き、日中はうとうとする様子が見られました。生活リズムが乱れて、余計に物忘れが悪化する悪循環も感じられたといいます。
薬や検査への不安も根強く、義父も「治験って、まだ承認されてない薬を使うんでしょ?怖いよ」と慎重な姿勢を崩しません。Aさん自身も「もうやめようか」と考えたことが何度もあったといいます。
何度も辞退を考えた末、“まず検査だけでも”と決断
それでもAさんは、半年かけて少しずつ家族に働きかけていきました。
焦点を「認知症」から「睡眠の悩み」へとずらし、「夜中に起きちゃって困ってるなら、一度ちゃんと診てもらおう」と提案。
治験は途中で中断できること、通常の診療以上に詳しい検査が受けられること、プラセボ(偽薬)の可能性もあること、専門スタッフから直接説明が聞けること――こうした安心材料を少しずつ共有しながら、ようやく「まずは検査だけでも受けてみよう」という流れになったといいます。
「何度も話し合って、時には後戻りもしました。でも“眠れないの、怖いんだよね?”と、本人の困りごとを起点に話を続け、その都度『すぐやめられるし、検査で状況を知るだけでもいい』と励まし合いました。そして、ようやく義母・義父も納得してくれて、家族の足並みがそろいました」とAさん。
家族の“心配”を“責め”と受け取らせない工夫、そして本人が納得できる「糸口」を見つけること。その積み重ねが、前に進むための第一歩となったのでした。
治験ってどんなことをするの? 内容をもう少し詳しく
ここで、Aさんの義母が参加した治験について少し紹介します。
Aさんの義母が参加した治験は、「睡眠と認知機能の関係」に注目した試験で、次のような内容が段階的に実施されました。
治験の主な内容
- 治験薬(もしくはプラセボ)の服用:毎日の服薬スケジュール通り、飲み忘れがないか記録
- 定期的な通院:診察、採血・認知機能テストなどを数回実施。通院は家族も付き添い
- 睡眠の記録:専用の睡眠活動量計やスマートフォンのアプリを使い、睡眠時間や生活のリズムを記録
- 副作用の確認と健康チェック:少しでも気になる症状が出たらすぐに治験コーディネーター(CRC)に相談できる体制が整っていた
このように、「ただおくすり(治験薬)を飲むだけ」ではなく、体調や生活の変化も含めて丁寧に診てもらえるのが治験の特徴です。
治験に参加してみて、実際どうだった?
親身なCRCのフォローで「想像以上に安心」
睡眠活動量計の装着やスマートフォンでの記録など、初めてのことに戸惑う場面もあったAさんの義母と義父。しかし、わからないことがあるたびにCRC(治験コーディネーター)に連絡すれば、いつでも丁寧にサポートが受けられたと言います。
Aさん自身も「血液検査や認知機能チェックなどが定期的に行われるので、むしろ普通の外来よりもしっかり診てもらえて安心だった」と話します。
治験に対して抱いていた“実験っぽくて怖い”という義父の不安も、スタッフから「使用される薬はすでに安全性が確認されている段階のもの」「プラセボの可能性もある」と繰り返し説明を受ける中で、徐々に解消されていきました。
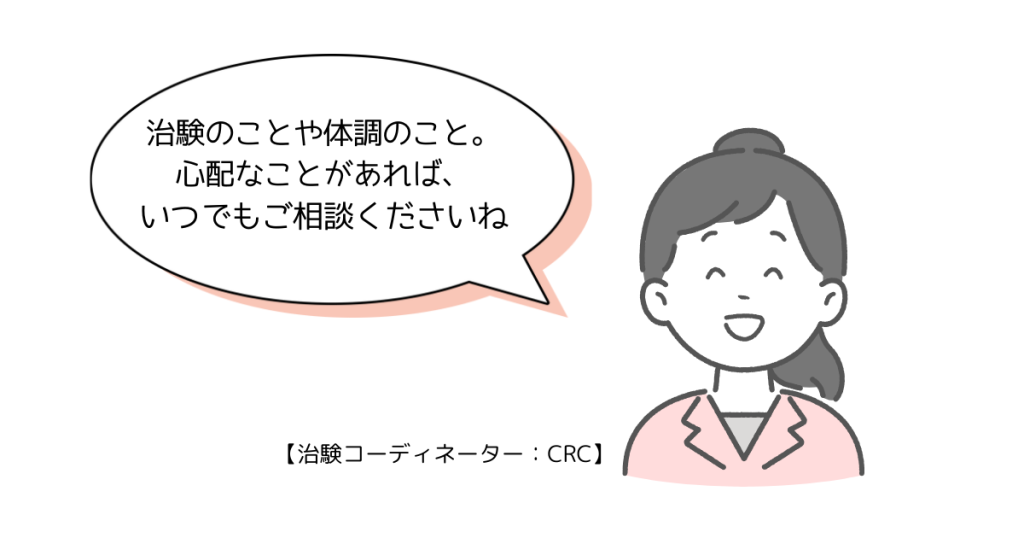
生活習慣の見直しに繋がり、家族全体で早寝早起き
治験では毎週のように「副作用はないか」「薬の飲み忘れはないか」とチェックされるため、家族全体が“生活を整える意識”を持つようになったそうです。
夜更かし気味だった家族の就寝時間も見直され、「今週も頑張ろうね」と声を掛け合う習慣が自然と生まれたといいます。義母にとっては、「薬が効いているのかは分からないけれど、“〇時に寝る”などの目標を立てることで、前より穏やかに眠れるようになった」という実感も得られたようです。
“認知症かも”を言葉にできるように
Aさんが感じていたとおり、一連の検査を通じて、義母には実際に認知機能の低下が見られました。検査結果が出て、医師から詳しい説明を受けることで、“気のせい”ではなく客観的に現状を把握できたのが大きかったといいます。
当初「自分は違う」と言い張っていた義母も、「検査の数字で言われたから、ちゃんと考えないとね」と前向きに治療を考えるようになったといいます。
治験が終了した後は、紹介状をもらい、大きな病院でさらに詳しい診断を受けることに。Aさんは、今回の治験参加は、本人と家族にとって「気づき」の機会にもなったと振り返ります。
Aさんから、同じように悩む家族へのメッセージ
「最初は『実験っぽくて怖い』『認知症なんて認めたくない』という義母と義父の気持ちに、私もどう声をかければいいのか迷いました。でも、認知症に関しては、少しでも早く治療に繋げたかったので、“夜中に目が覚めて困っているんでしょ?”という睡眠の悩みを軸に話をしたことで、少しずつ前向きになってくれたんです。
“まず検査だけ受けてみよう”と伝え続ける中で、治験はとてもよいきっかけになりましたし、実際にはとても丁寧に診てもらえて、安心できました。
もし同じように悩んでいるご家族がいたら、“まず睡眠を見てもらおう”という切り口で、一歩踏み出してみてほしいです。」
まとめ:嫌がるご家族を受診へ導くヒントは、まず「睡眠」かもしれない
「年のせいだから」と見過ごしがちな物忘れ。しかし、その裏には認知症の初期サインが隠れていることもあります。
今回のように、“眠れない”という身近な困りごとをきっかけに受診し、結果的に認知機能の低下に早く気づけるケースも少なくありません。
治験は、自由意志での参加が原則であるため、途中で参加を辞退することは問題ありません。「丁寧な説明やフォローがある」などは、家族やご本人にとって安心材料となることも多く、初めての受診のハードルを下げる手段にもなり得ます。
治験に関心はあるけれど、「どこに連絡すれば?」「何を聞かれるの?」と不安な方へ
Aさんのケースをもとに、家族が働きかけて治験に参加する際の具体的な流れを紹介します。
- ①ウェブ・電話で治験の申込を行う
- 今回のケースは、Aさんがスマホで治験情報ページを見つけ、義母に代わって「トライアド治験ネット」から申し込みをされました。
- ②電話確認・受診日程の調整
- 申し込み後、スタッフから連絡が入り、詳しい症状や治験に参加できるか条件確認を行います。ここで、家族応募の場合は、「認知症が心配な家族がいる」と相談されるとスムーズです。
参加条件に合致する場合は、医療機関の治験コーディネーターからお電話がありますので、初回の診察日を調整していただきます。
- ③初回受診(治験の説明・同意確認)
- 医師・CRCから詳しい説明があり、疑問点もその場で聞いていただけます。
家族が同席*すると意思疎通や理解も進みます。
*治験によっては、同席が必須な試験もあります。
- ④事前検査(心理検査・採血など)
- 負担のない範囲で、初回受診時に複数の検査を実施します。
- ⑤治験への本参加
- 睡眠状況等の検査期間を経て、薬またはプラセボを一定期間服用・通院いただきます。
- ⑥治験終了。継続治療の相談
- 治験の終了時には、継続治療について相談いただくことができます。
以上が基本的な流れです。
詳しくは下記リンクから、【トライアド治験ネット】の治験ボランティアにご登録ください。
登録前に相談がしたい方は【お問い合わせ】よりご連絡ください。
注意事項・免責
この記事はAさん一家の個人体験談です。効果や結果は人によって異なり、治験への参加を推奨するものではありません。
ご自身・ご家族の体調や症状については、必ず医療機関にご相談ください。
記事内の人名やエピソードはプライバシー保護のため一部変更しています。